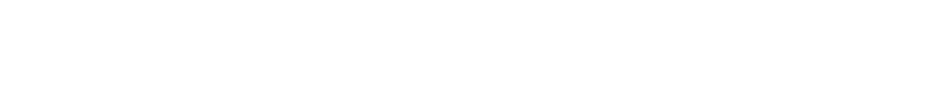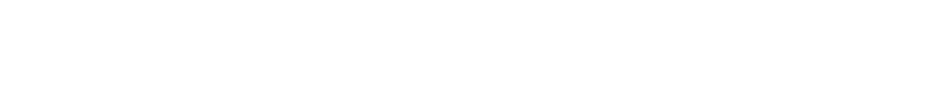|
|
|
 |
 |
徒然草々 |
 |
|

| * いのこ 解説 * |
|
|
※句いのこ 解説 ※
いのこを
検索してみると...
亥の子
亥の子祭りのメイン行事。縄を結びつけた石を数人で持って、亥の子のうたを歌いながら地面をたたき固めます
起源は平安時代
「亥の子祭り」は冬の風物詩として親しまれています。毎年亥の月、亥の日に子沢山を象徴する猪をかたどったお餅を朝廷に献上していた慣わしが何時しか庶民の間に広がったとされています。家内安全、子孫繁栄を願い町内の家々を亥の子石をつきながら家内繁盛を願うお祭りです。【亥の子、亥の子、亥の子餅ついて
旧暦十月上の亥の日のことで、古来この日から火燵(こたつ)を開く習慣があったそうですし、西日本では収穫祭とも言われ、この日に田の神が去っていくと信じられていました。また、「亥の子の祝い」といって、この日の亥の刻に亥の子もちを食べると万病を除くとか、亥を猪(いのしし)のことにとり、猪が多産であることから子孫繁栄を祝うためとも言われています。
この日の夜 わら縄に石を結びつけたものや、わらを束ねて固めた棒で、門前の地を打ちながら厄(やく)除けの文句を唱えて各家々を回って歩くきます。
臼杵市でもこうした亥の子の行事が、市内の各地で行われていましたが、最近は指導する人もなくなり年々廃れてしまいました。いまでは、十月から十一月にかけて坪江などの上浦地区や大浜などごく一部の地区でしか行われていませんが、こうした伝統行事はいつまでも残していきたいものです。
☆ 元に戻る ☆
亥の子唄
ツーカイナ ツーカイナ 亥の子もちつかんもにゃ鬼生め 蛇生め 角生えた子を生め 大っきい子も こんめえ子も 杵とって投げて たなから タンヨムさんがたなから落ちて タンス踏み割り 猫んケツければ ナタで足切る無精な男 ヘンテイヘンテイ ユーテイ 一つやりましょう 大黒さんという人は 二でニッコリ笑うて 三でさかづきさし合うて 四ッ世の中よいように 五ッいつものごとくなり 六ッ無病息 災に 七ッ何ごとないように 八ッ屋敷を広めて 九ッここに蔵を建て 十ラッ京に上り 宝物をかちく だき あなたの蔵に ちょうどいっぱい ユーエイ
おいのこさん(亥の子祭り)は、日本各地で行われています。
岡山県、愛媛県の一部、九州の一部で行われています。 どこの地方も
旧暦10月の最初の亥の日に行われます。 地面をうちつける方法は
地方によっては、大きな石を 5人から6人が縄で縛り付けた
ひもを持って亥の子歌を歌いながら調子を取りながら石を打ち付けます。
八多喜(粟津地区)と同じように稲ワラをたばねたワラスボを使って
地面を打ち付ける地方もあります。
この行事は古くからあり、いのしし(猪)の多産に結びつきに加えて
農村部では農業の豊作への願いから行われています。 農業の
機械化とともに廃れていった地方もあります。
11月の”亥の日”の夜、集まって、漬け物石のようなものに4〜6本のロープ(またはカズラ)をつけて、うたを唄いながら、石を空中に上げたり、地面にたたきつけたりを繰り返します。)
先に氏神様をまわり、その後、集落全戸の庭で石をついて厄を払います。ごほうびにおかしやお金をもらいます。
聞くところによると、亥の子は中国地方の風習のようです。我が作東町は兵庫県との境の町ですが、兵庫県には無いんでしょうか?四国には?(97.5.2四国にあることがわかりました)
また、歌詞が町内でもかなり違うようですが他県ではどう唄うのでしょうか?
☆ 元に戻る ☆
作東町のある集落ではこう唄います。
いまだに歌詞の意味がわかりません(^^;)
いのこのようさ もちつかんもんは おにうめこうめ つーののはえたじゃうめ えいとさいと さいとこもちくわそうか
になります。 さいとこ餅ってどんな餅なんだろう。
まだまだあるぞ
いのこのようさ もちつかんもんは おにうめ こうめ つののはえたじゃうめ かーしもさがればじょうさんてんのう まわれ まわれ はんじょせー はんじょせー
てな感じです。
☆ 元に戻る ☆
調査隊員の情報により明らかにされた衝撃の事実!(掲示板書き込みより)
●5月2日:中国地方だけでなく愛媛県にもあることが判明!
調査隊員No002 愛媛県高岡さんより情報
我が愛媛県にも亥の子はあります。県内でも石を使ってそちらと、同じ用にする地方と、私の町(伊予郡砥部町)のように、稲藁を直径4〜5センチに束ねてきつく縛り、棒状のもので、独特の歌(そちらとはちがうようですが)にあわせ、各家庭の玄関先で、地面を叩き、五穀豊穣、家内安全などを祈願してしていきます。とりあえず、以上
●5月4日:中国地方でも鳥取県と島根県には無いことが判明!(少なくとも出雲市と鳥取市にはない)
☆ 元に戻る ☆
調査隊員No003鳥取市こんどうさんより情報
出雲出身で鳥取市に住んでいますが
いのこという行事は聞いたことがありませんが...中国地方でも山陽側だけではないんでしょうか?
●8月吉日:なんと九州大分市あたりでもいのこが・・・
調査隊員No.004大分市からの報告です。
「大分県の民俗」
第一法規出版(株)昭和48年発行 著者大分県杵築市在住 染矢多喜男 によれば、
10月の亥の日をイノコ(亥の子)という。亥の日が三度ある場合は、それぞれ武士
・百姓、町人、女・男・家畜のイノコだという所もある。土地によっては、歳徳さ
ま・大黒さまが家に帰られる日であるという。
イノコには餅をついて祝うことは、豊前地方(大分県の北部2郡と福岡県南東部の
区域)を除いて広く行われている。国東半島では、ついた餅を枡に入れて神棚や俵
の上に供える。イノコの晩には、イノコウタを歌いな
がら地をついたり、打ったりして、餅・銭・菓子などをもらう。イノコツキ・イノ
コウチ・イノコという。もぐらの害を避けるためだという。イノコツキは杵築市(
大分市より別府湾岸沿いに3・40キロメートルの距離)のものがもっとも整った形を残
している。イノコウタは土地によって変化があるが、「イノコモチ祝わん者は、鬼
生め、蛇生め、角の生えた子生め」という部分はほぼ共通に持っている。イノコに
使った御幣や藁束は蛇除けや豊熟のおまじないにしている。「イノコモチを食わに
ゃはえは去らぬ」という所が多い。
大分市内のはずれに居住したいるにで、現在、杵築市で上記のような行事
が行われているかどうかは不明です。昭和7・8年頃、大分市近郊でも
集団で夜イノコ行事(イノコ餅をもらってあるく)が行われていた気憶があります
。あることが判明いたしました。
歌詞を聞いてみると、この作東町とほとんど同じじゃあーりませんか。いったいいのこはどのような広がりを見せているのでしょう。
☆ 元に戻る ☆
●11月26日:調査隊員No.005高知のしおたさんから報告です。
滋賀県内では野洲郡中主(ちゅうず)
町と、湖西の安曇川町・今津町に亥の子が残っており、亥の子唄は やはり「鬼生め・蛇生め」です。
高知県には亥の子はありませんが、愛媛県には石で搗く型も藁棒で
叩く型のものもあり、宇和地方では数え唄の亥の子唄がたくさんあります。
●1月14日:調査隊員No.006のわたなべさんから報告です
岐阜県でのことです。昔のことなので,詳しくは覚えていませんが,特にみ
んなが集まって何かするということはなかったように 思いま す。
各家庭で,大きなおはぎを作って(2つ合わせると子 供の頭くらいになるかな),夜,亥の方向に向かって
(家の場 合は納戸でした)お供えします。
翌朝,お下がりを皆でいただきます。時期は12月の最初か二番目の亥の日です。
おはぎは,なぜかおひつのふたに載せてお供えをします。
●1月14日:調査隊員No.007の愛媛県民さんから報告です
亥の子についてですが、それぞれ宇和の中でも違うようです。そこで、宇和の坂戸の亥の子歌を掲載します。
坂戸の亥の子はこうです。はじめに、家にいって
『亥の子を祝いまっせ』 と大声で言います。そして
『祝いましょ 祝いましょ お大黒様は
一が俵ふんまえて 二でにっこり笑うて 三で酒作って 四つ世の中良いように
五ついつものごとくに 六つ無病息災(むびょうそくさい)に 七つ何事無いように
八つ屋敷をつき広め 九つ米倉(こぐら)を築き建てて 十でとっくり納まった
えいえいやーな』
と歌います。そのあと
「うぐいす」「この屋敷」「白ねずみ」「お扇子」の中から一つ歌います。(全部書くと長くなるので省略します)
いちよう、この四つが亥の子の歌のメインのようなものです。
(はぶいちゃったけど・・・・)
で、おわりに
『亥の子の餅を祝うなら 西も東も金の山 南も北も米の山 悪病災難払いのけ
福の神は舞い込んだ 舞い込んだ』
と歌い、お金をもらってつぎの家に行きます。ほかの地方には、ちながを使うというとこもあるけど
坂戸は石を二つ使います。
●4月23日:調査隊員No.012の清水さんからの報告です。
僕は、愛媛県宇和島市出身です。
住んでいた町は元結掛ですが、僕はこの行事は
宇和島とその周辺だけだろうと思っていました。
しかし、あなたのHPを見てとても驚きました。
まさか、県内はおろか、本州や九州でもやっているとは
思ってもいませんでした。しかも、石をつくという形式は
全く同じで驚きました。
さて、僕が住んでいた元結掛では、おなじみの
数え歌のほかにいくつか歌がありました。
僕は歌はうる覚えだったので全部は分かりませんので
一部だけ書いておきます。
♪おいたやのぅ おいたやのぅ
♪なにか薬はあるまいか
♪海にはえとる マツタケと
♪山に転がる ハマグリを
♪???????????
♪明後日つけたら 今日治る
♪忠臣蔵のごだんめは
♪おかるのうった????
♪よいちべえの????
(後は忘れました・・・)
すいません、書いてみるとほとんど覚えていませんでした・・・
僕らの地方では「おいのこさん」と呼んでいたのですが、
良く考えると歴史的に非常に興味あることですよね。
・どこが発祥の地なのか
・なぜ石をつくのか
など疑問は尽きないです。
☆ 元に戻る ☆
●11月2日:調査隊員No.016のヒロさんからの報告です。
の里は愛媛県八幡浜市千丈地区ですが
亥の子歌は次のように歌います。
♪
今晩のお亥の子は
一に俵を踏んまえて
二でにっこり笑うて
三で酒を造って
四つ世の中よいように
五ついつものごとくに
六つ無病息災に
七つ何事ないように
八つ屋敷をひろめたて
九つ小倉を建てならべ
十でとっておさめた
エ−イエ−イ亥の子♪
数え歌部分はほとんど同じですが
はじめと終わりは地域によって異なりますね
以前東京でこの歌を歌ったら大ウケしました。
☆ 元に戻る ☆
愛媛県は亥の子がいっぱい残っているのですね。
はじめてまして。
今日は亥の子さんの日だったので
何気に検索していたらたどり着きました。
私は島根ですが、こんな歌ですよ。
い〜のこさんの晩に 祝わぬ者は〜
蛇うめ〜 こうめ〜
角の生えたこうめ〜
おみこしを担いで一軒ずつまわってきます。
あちこちに亥の子さんがあるんですね
うちの地方では、年々少子化が進み女の子も祭りに参加しています。歌は愛媛県のなおきさんのところのものと、とてもよく似ています。『お亥の子さんというひとは』の個所がうちのほうでは、『だいこくさまという人は』となっています。
また、この『だいこくさま』の前に(亥の子うた)が歌われます。この(亥のこうた)しゃれにならないほどたくさんあって、とても全部は書けませんが一部紹介したいと思います。
<亥の子うた>
ひとつエー ひとつうったいましょ ヨイサン ヨイサン
はばかーりなーがらエー
うたのエー うたのあやまり ヨイサン ヨイサン
ヤレコラ がーめんなされー
瀬戸のエー 瀬戸の明神様 ヨイサン ヨイサン
どおゆーておーがむエー
どおかエー どおかこの子が ヨイサン ヨイサン
ヤレコラ まーめなーよにエー
鶴とエー 鶴と亀とが ヨイサン ヨイサン
どおゆーて あーそぶエー
おいえエー おいえごはんじょ ヨイサン ヨイサン
ヤレコラ ゆーてあーそぶエー
さくらエー さくら三月 ヨイサン ヨイサン
あやめーは五ー月 エー
咲いてエー 咲いて歳とる ヨウサン ヨイサン
ヤレコラ うーめのー花エー
以下続々と続きます。今回はこの辺で失礼します。私が教わっていないうたもたくさんあると思うので調べてみたいとです。何か発見したらお知らせします。
岡山県勝田郡奈義町の上高円で歌う歌です。
亥の子、亥の子、亥の子の夜ぉさ
餅搗かん者は、鬼産め、蛇産め、角生えた子ぉ産め
えっさ、ほいさ、さいころ餅喰わせ、おまけ、おまけ
亥の子の石をまつってある神社に夕方集まって、
神社の掃除をした後、家を訪ねてまわります。
『亥の子を突きに参りました』と言って地面を5人くらいで突きます。
突いたら、家の人からお金を貰います。だいたい2、3千円でした
貰ったお金は神社で6年生がみんなにわけます。
昭和20〜30年代はお菓子や野菜を貰っていたそうです。
しかし改めてこの歌詞を考えてみると、なんとも怖い気がします。
1kmも離れてない隣の地区でも歌が違ったりします。
また、私のふるさと海田町では、
亥の子 亥の子 亥の子もちついて
祝わんものは 鬼うめ(産め?)蛇うめ
角生えた子うめ やっさのしりを
ゆでゆでたいて それをそれを・・・
☆ 元に戻る ☆
私の町にも亥の子があります。(滋賀県安曇川町)
唄は、
祝おうかなー(掛け声)
亥の子のよさり餅つかんもんは鬼うめ蛇うめ角のはえた
ごんめ、いとはんぼんさん寝てかいな。
もひとついおうて帰りましょ。ぺったんこぺったんこ
ぺったんぺったんぺったんこ。
亥の子
秋も深まり11月に入ると,亥の子を心待ちにした。百科事典によると,亥の子の行事は中国に起こり,平安宮廷にもたらされたという。そんなに古い伝統をもつ行事だとは知らなかった。もとは,旧暦10月の亥の日に行われた。
今日,亥の子が全国的な行事として残っているのかどうか,それは知らない。少なくとも松山地方では,代々引き継がれ,今に至っている。私の知る限り,今では亥の子は新暦の11月だ。
11月の亥の日であったのだろう,私の記憶では,亥の子は11月に3度行われた。一の亥の子,二の亥の子,三の亥の子などと呼ばれていたように思う。干支の具合によっては2度しか行われない年もあるはずだ。日の暮れが釣瓶落としに早くなり,朝晩の寒さが身にしみるようになったころ,待ちに待った亥の子がやってくる。
日暮れ時,藁(わら)縄を周囲にたこの足のようにつけた石を下げて,一軒一軒を回り,家々の玄関先でその石を搗(つ)くのである。家を建てるときの地固めのような案配に搗く。石は角を丸く削った太鼓のような形に整形されていて,大きさは,直径30センチ,高さ15センチほどだったろうか。それを7,8人が 歌を歌って拍子を取りながら搗く。縄を持つことのできないコは,手拍子を打ったり,足を踏みならしたりしながら,一緒に歌う。
搗き終わると,その家の奥さんが お菓子の入った袋をくれることになっている。こうして町内の家々を全部まわり終えると,もらったお菓子をみんなで分けあい,家路につくのである。
ほんの1時間ばかりで終わる他愛もない行事であるが,これがこの時期の大きな楽しみだった。夜寒を感じる夕暮れ時に,大勢集まってくるだけで,昼間の遊びとはひと味違った,「晴れ」の気分を味わうことができたのだ。寒さに身を縮ませながらはしゃぎ回る,これだけで十分楽しいのである。
亥の子には独特の歌があった。その歌を歌いながら石を搗くのである。もう何十年も昔のことだから,歌詞は半分以上忘れている。思い出すままに記しておくと,
亥の子,亥の子,亥の子餅ついて,祝わんものは,お恵比寿 (おえべっさん)にゆうてやろ。それ,一で一緒に歌いましょ(?),二でにっこり笑ろうて,三でさかずき…(?),四で…(?),五ついつものごとくなり,六つ昔のごとくなり(?),七つ何事ないように,八つ屋敷を建て広げ,九つ小倉を建て広げ(?),十でとうとう…(?)。…(まだ少し歌詞は続く)。
こんな歌であった。覚えている方があれば,教えて下さい。
☆ 元に戻る ☆
百科事典によると,「中国では、この日の亥の刻に、ダイズ、アズキ、ササゲ、ゴマ、クリ、カキ、糖の7種を混ぜた7色の餅を食うと、無病だという俗信があって、それが平安時代の宮廷に取り入れられ、室町時代には、白、赤、黄、栗、胡麻の五色の餅をつくった。この餅は宮中や将軍に献上するものであったが、のちには同時に宮中や将軍から臣下に下賜され、あるいは貴族同士が互いに贈答しあうことにもなった。…。亥の子餅は,…,女官たちが搗く風習もあったし、宮中への餅は、天皇自ら搗くことが古くからの慣例であったらしい。」とある。
かつては,亥の子の日に本当に餅をついていたということのようだ。それがいつの頃からか,石で地面を搗く形に変容してきたのである。あるいは地域によっては,石ではなく,一人一人が藁束で地面をたたく(搗く)というところもある。それにしても,亥の子は長い伝統に支えられた,道教的色彩の濃い行事なのであった。
こうした行事が,民間で長く伝えられてきたというのは不思議である。松山で,市が音頭をとって一斉にやるというような,大がかりなものではない。本当に細々と地域の伝統として守り抜かれてきた行事なのだ。だから,町内によってはまったく亥の子と無縁なところもあるはずだ。
☆ 元に戻る ☆
11月16日、お亥の子様でした。
土地、土地で多少風習は異なるものの、宇和島では昔から行われるの風習です。
この日は、たまたま家に居て、犬がワンワン吠えるので、外に出たら、お亥の子様(おいのこさま)でした。漢字で覚える前に言葉で覚えるので、オイノコサマ、というけったいな行事だと思っていました。
生半可な知識で済みませんが、11月の亥の日に 亥の子石を抱えて、各家庭を回り、許しを得て、その家の前の道路で、はやし唄を唄いながら、縄をひいたりゆるめたりして、石を地面に打ち付けて、その家の無病息災を祈願する行事です。
佐賀地区の亥の子)
佐賀の中でも東・中・西の3地区に分かれます。
地区内の家庭を回ります。
「どうづき」と呼ばれる電柱を短く切ったような円柱(直径25センチ、長さ70センチ)に4本の
柄がついたものを持って、2,3名で家の庭先の地面をリズムに合わせて突きます。周りの子
供たちは、亥の子歌を元気に歌います。歌詞は地区によって少しずつ違うので次のページで
紹介します。
☆ 元に戻る ☆
いのこさま
毎年旧10月の最初のいのししの日に、熊野市五郷町で行われる行事。
天保時代頃から始まったもので、農業の豊作のお礼として行われている。その日はますを使わないように、餅を入れてそなえる。
昔は、各家庭で前日餅つきをして、当日の夜「いのこいのこ」と祝い、こどもが餅をもらいに各家庭を歩いた。また当日は農作業を休んだ。今は餅はつくが、こどもは歩かなくなった。
いのこいのこ 今夜のいのこ めでたいいのこ 鶴や亀やが まいさがれ
旧10月の亥の日には全国的に稲の刈り上げ行事が見られる。この日、家々を石や藁束で地面を突いてまわり、餅などをもらう行事が広くおこなわれていた。子供たちは神様と見なされ、神様が家々を祝福して歩いたと解釈されている。これが鬼決め遊びとしてわらべうたに取りあげられた。この行事は南九州でも盛んだが、この歌詞は鹿児島のものではない。
香々地地域の心あたたまる伝統行事
大分県豊後高田市御玉114
香々地地域の伝統行事「亥の子(いのこ)」が行われました。「亥の子」とは、出産や結婚・新築などの祝い事があった家々の玄関先で「いのこ、いのこ、いのこ繁昌、子繁昌、ここの(赤ちゃん・お嫁さん・お家)を祝いましょう」などと口々にはやし歌いながら、手にした“いのこぶち”(ワラを束ねて作った長さ80cmくらいの棒状のもの)で地面をバッタンバッタンと叩きます。すると、その家の方から祝ってくれたお礼にと お菓子やジュースなどが振る舞われます。この日は、多くの家族連れなどがお祝いに訪れ、準備していた約400人分のお菓子などが1時間も経たずになくなる家庭が何件もありました。お祝い事のあったご家庭の繁栄を心よりお祈りいたします。
いのこ. いのこをつきました。 おもたかったけど みんなで ...
おいのこさま
いのこのようさ もちつかんもんは おにうめ こうめ
つののはえたじゃうめ かーしもさがればじょうさんてんのう まわれ まわれ はんじょせー はんじょせー
... 僕らの地方では「おいのこさん」と呼んでいたのですが
☆ 元に戻る ☆
2006年10月30日
ハロウィンは*いのこ*に似てる
「今が旬の話(3498)」 [ 里山・歳時記 ]
ハロウィン(Halloween)は、キリスト教の諸聖人の日(万聖節)の前晩(10月31日)に行われる伝統行事です。
諸聖人の日の旧称"All
Hallows"のeve(前夜祭)であることから、Halloweenと呼ばれるようになりました。
古代のケルトの人たちは、収穫の季節である秋が深まるにつれ、どんどん日が短くなり、夜が長くなっていくのは、Samhain(あの世を支配する王)が太陽の光を奪ってしまうからだと考えました。
そこで、収穫物をお供えして崇め、死者の魂をなだめ、大きなかがり火を焚いての暗さに対抗し、翌年の幸運を祈りました。
そのかいがあって、冬至を境に日が長くなり始め、彼らの願いが聞きいれられたと喜びました。
この夜は死者の霊が家族を訪ねたり、精霊や魔女が出てくると信じられていました。
これらから身を守る為に仮面を被り、魔除けの焚き火を焚いたのです。
ハロウィンを日本のお盆に似てるという人がいるが、私は*いのこ*にそっくりと思う。
11月. いのこもち. 五條市.
いのこもちは「亥の子餅」または「亥猪餅」とも書く。
農耕行事のひとつで、旧暦の10月の亥の日に餅をついて食べると万病を払い、 ...
その年にとれたもち米に里芋を少し入れて餅をつき、つきたての餅に餡(あん) ...
神崎の亥の子祭り
神崎学区では「亥の子祭りを」毎年11月に行っています。町内会によって多少の違いが有りますが概ね11月の第二日曜日にやられているようです。「亥の子大明神」のお宿は、その年に新築されたお宅にお願いしたりしていましたが、ほとんどの町内会では毎年決まった場所に祭壇を設置し「亥の子大明神」をおまつりしています。
河原町の「亥の子祭り」は昭和20年代の後半にはやっていた記憶があります。戦後に被爆から復興された町でいち早くお祭りが復活されたのだと思います。
この「亥の子祭り」の起源は古くて、平安時代に遡るようです。当時の朝廷で毎年亥の月の亥の日に猪をかたどった御餅を献上して繁盛を願った風習が何時の日にか庶民の間で行われるようになったようです。猪が多産系でその家々が栄え繁盛するように町中「亥の子石」をつきながら練り歩きますが、もともとは農業の神様のようです。町内を回りながら「い〜のこ♪ い〜のこ♪ い〜のこ餅ついて 繁盛せい 繁盛せい」と 歌います。昔は 獅子舞やこどもが扮した赤鬼や青鬼が一緒に回っていましたが最近はやっていません
☆ 元に戻る ☆
【亥の子とは】
亥の月、亥の日、亥の刻に餅を食べることで無病のまじないとする「亥の子」行事は、中国伝来の習俗で、すでに平安時代には、宮中の年中行事としてわが国に伝わっていた。陰暦10月は、十二支に当てはめると「亥の月」にあたり、「猪が多産なので、とくに女性がこれにあやかって餅を贈りあい祝う」という俗信が、農村では農作物の収穫期と重なり、豊穣を祝う収穫祭の行事として各地に定着した。
久美浜町須田では、旧暦10月の亥の日に餅をついて亥の子を祝う。この日は、田の神が一年の仕事を終えて家に戻られる日といい、家人は新米を用いて白餅を作り田の神をもてなすのである。田んぼから家に戻った神は臼(うす)でひと休みし、家のタカ(※)に上がって一冬を越し、そして春になると再び田に戻るのだという。当地では、干支(えと)は子からはじまり亥に終わることから、俗に「亥の子」は一年の締めくくり、新年を迎える重要な折り目と伝わる。作物の稔りを一年のサイクルとした「稔(とし)」の観念がうかがえる。
亥の子の餅は10cm程の白餅で、昔は一斗七臼で200個程の餅を家内じゅうでつくった。「やったりとったり亥の子の餅かな」といい、嫁には重箱につめた餅を持って里帰りさせ、しばらくは農作業も休んだ。帰りにはお返しにと、亥の子餅をもらうのが古くから慣習だった。
|
|
|
 |
|

|
|